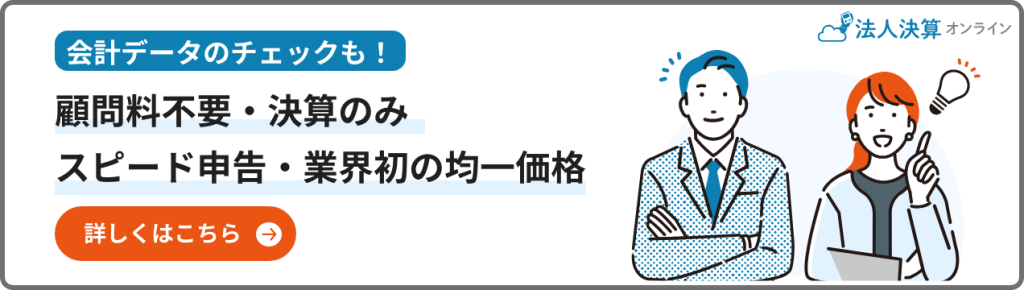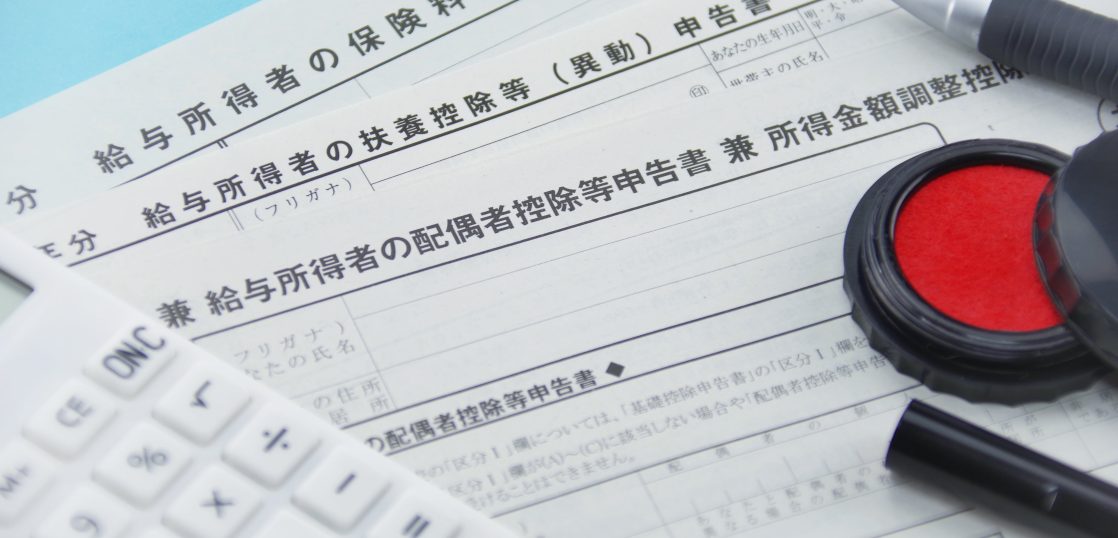年末になると、企業では年末調整をおこないます。年末調整の役割や手続きの内容をくわしく理解しているかたはいがいとすくないかもしれません。経理や総務の担当者だけではなく、経営者も年末調整についての知識をもっておくことが大切です。年末調整の目的やながれなど会社がおこなう内容をくわしく解説していきます。
年末調整とは?
年末調整とは、企業が従業員の給与などから毎月天引きした所得税と、本来支払うべき所得税の金額を調整し、確定させる業務のことをいいます。
企業で働いている人は、毎月の給与から「所得税」が天引きされていると思います。会社が給与を支払う際、従業員の給与などから所得税を徴収することを「源泉徴収」といいます。源泉徴収額は概算のため、後から過不足金額が発生します。本来徴収が必要な1年分の所得税総額を再計算し、これまで源泉徴収した合計額と、あらためて照らしあわせて「過不足金額」を調整することが「年末調整」です。もし、源泉徴収額に余分があった場合は差額を還付し、不足があれば追加徴収されるという仕組みになります。
わかりやすくいうと、「前もって毎月給与からおおよその所得税を天引きしておくため、年末に正確な額を計算して、多く取りすぎていたら返す、足りなかったら追加で徴収する」という内容になります。
「なぜ最初から毎月正確な金額で天引きしないのか?なぜ年末に調整するのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。概算の金額でしか源泉徴収ができない理由としては、所得税は1年間(1月1日〜12月31日)の所得に基づいて税率・税額の変更があげられます。そのため、年末にならないと個別の税額を確定できません。1年の途中で給与金額の変更や転職、扶養にかかわる家族構成の変更などが生じた場合や、給与や賞与の控除、社会保険料などの各種保険料を支払っている場合にも、過不足金が発生する可能性があります。
年末調整の対象者は?
企業が給与を支払っているすべての従業員が、年末調整の対象者です。正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトも対象になります。派遣社員に関しては、雇用している派遣元が年末調整を実施します。
12月に年末調整をおこなうのは、その年の「扶養控除(異動)申告書」を提出している人、1年を通して勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人になります。ただし、以下のケースに該当する場合には、年末調整の対象から除外されます。
- 従業員・役員とわず、給与所得が2,000万円を超える場合
- 災害減免法という法律によって、所得税の支払い猶予や還付をすでに受け取っている場合
- 副業などで2カ所以上の収入源があり、他の給与支払い者に扶養控除等(異動)申告書を提出している場合
- 非居住者
- 日雇労働者など、継続して雇用されていない場合
- 年末調整の対象から外れた場合
は、確定申告が必要になります。
また、以下のケースに該当した場合には、12月以外でも年末調整の対象になります。
- 海外支店などに転勤した場合
- 死亡により退職した場合
- 著しい心身の障害によって退職した場合
- 12月の給与等の支払いをうけた後に退職した場合
- パートタイマーとして働いており、その年に支払われる給与総額が103万円以下の方が退職した場合
年末調整を行なわずに従業員から正しい税額の徴収をしない場合や、年末調整を実施したにもかかわらず追加徴収を納付しなかった場合などは罰則があります。もし、従業員側の都合で、書類の紛失や提出の遅れがあった場合は、従業員本人が確定申告をすることで対応が可能です。
年末調整の際に提出が必要な書類は?
年末調整で必要になる書類は、大きくわけると「従業員からの提出書類」と「会社から税務署や市町村に提出する書類」になります。
従業員からの提出書類
「従業員からの提出書類」はおもに以下の3つです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
これら書類は原則として従業員本人に記入してもらいます。これをもとに年末調整の計算をし、従業員ごとの源泉徴収票を作成します。
会社から税務署や市町村に提出する書類
「会社から税務署や市町村に提出する書類」は、以下の4種類の書類です。
- 支払調書
- 法定調書合計表
- 源泉徴収票
- 給与支払報告書
これらの書類は、年末調整の計算が完了したあと作成します。
年末調整のながれ
年末調整の大まかなながれは以下の3ステップになります。
【STEP1・11月ごろ】従業員に必要な書類を配布・説明・回収する
前項で紹介した必要書類(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書など)を配布します。
従業員がそれぞれ内容を記入し、生命保険料控除証明書など、各々が必要な添付書類をそえて提出してもらいます。きちんと提出期限をきめておき、間に合うように回収しましょう。
【STEP2・12月〜翌1月ごろ】年末調整に必要な徴収額の再計算をおこなう
従業員からの提出が必要な書類の回収と並行して、さまざまな再計算をおこないます。再計算が必要になるのは以下の項目です。
A)給与総額と徴収額の計算
対象となる従業員の、1月〜12月の間に支払われた給与や賞与の総額と、源泉徴収した徴収税額の総額を計算します。年の途中で入社した従業員がいる場合、その年に前職での収入があれば、前職分も年末調整の対象になります。この場合、前職の源泉徴収票が必要になるため、入社時に提出してもらっておくと良いでしょう。
B)給与所得控除後の金額の計算
「給与所得控除」とは、会社員の収入からさしひかれる控除のことです。会社員にも必要経費があるとみなすことで、従業員の所得税などを計算する際、一定額を法律で定められた必要経費として給与からさしひけます。Aで計算した給与総額に応じて給与所得控除額を計算し、給与総額からさしひくことで、給与所得控除後の金額を計算します。
C)各種所得控除の合計額の計算
従業員から提出された控除証明書等をもとに、各種所得控除額を正しく計算します。主な証明書は以下の6種類です。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 配偶者特別控除申告書
- 自社の給与・賞与(ボーナス)からの社会保険料控除額の情報
- 従業員が加入する生命保険・地震保険などの保険料控除証明書
- 給与・賞与以外で支払った社会保険料の保険料控除証明書
- 住宅ローン控除のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
D)課税給与所得金額の計算
「課税給与所得金額」とは、納めるべき所得税を計算するためのもとの金額です。BからCをさしひくことで、課税給与所得金額を計算します。
E)算出所得税額の計算
Dで計算した課税給与所得金額から、国税庁の公式サイト「算出所得税額の速算表」を参考にして、算出所得税額を計算します。
F)住宅ローン控除額の控除と年調所得額の計算
住宅を購入して1年目の場合は、年末調整の対象とならない確定申告の必要があります。2年目以降からは、年末調整での住宅ローン控除が可能です。Eで計算した算出所得税額から、住宅ローンの控除額をさしひいたものが年調所得税額です。
【STEP3・1月末まで】過不足分を給与で調整し、税務署に源泉所得税を納付する
年調所得税額の計算がすんだら、過不足分を給与で調整します。調整した結果をふまえ、税務署や市町村に提出が必要な書類を作成します。
G)年調年税額の計算と過不足額の還付・徴収
Fで計算した年調所得税額に102.1%をかけると「年調年税額」が算出されます。Aで算出した源泉徴収税額の総額が年調年税額よりおおい場合は差額を還付します。反対に、年調年税額より少ない場合は差額を徴収することになります。
H)所得税徴収高計算書の作成
税務署への提出が必要となる所得税徴収高計算書を、Gを反映させて作成します。
I)源泉所得税の納付
Hで作成した所得税徴収高計算書の提出とともに、1月10日(納期の特例をうけている場合は1月20日)までに「源泉徴収税」を税務署に納付します。納期の特例を申請している場合は、半年分の源泉徴収税を納付します。年末調整の結果、還付金の調整が確認できれば、差額分は源泉徴収税で調整されます。
J)源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書の作成と提出
年末調整後におこなう処理として、従業員へ精算したあとには、以下3つの書類の作成・提出をおこないます。
- 源泉徴収票(給与支払報告書)を作成
- 法定調書合計表と、必要条件に該当する従業員の源泉徴収票を税務署へ提出
- 給与支払報告書を各従業員の所在地となる市区町村へ提出
会社は1月31日までに、源泉徴収票を本人に交付する必要があります。
まとめ
年末調整で気をつけたいことと注意点
年末調整は短期間で大量の書類を処理する必要があり、時間的余裕を持つことが重要です。複数人でのダブルチェックが望ましいです。法改正の影響を受けやすく、毎年手続きや計算方法が変わる可能性があるため、担当者は変更点を事前に理解しておくべきです。
小規模法人や副業での経営者は、経理にかかる時間と予算を抑えたいと考えるでしょう。年末調整に関する知識を身につけることで、自分で処理できる範囲が広がります。しかし、従業員が増えると年末調整の手間も増えるため、場合によってはプロに相談するのが効率的かもしれません。必要な時に適切な予算配分をすることが大切です。
法人決算オンラインでは、オプションサービスで年末調整を行っています。詳しくはこちらの料金ページをご覧ください。