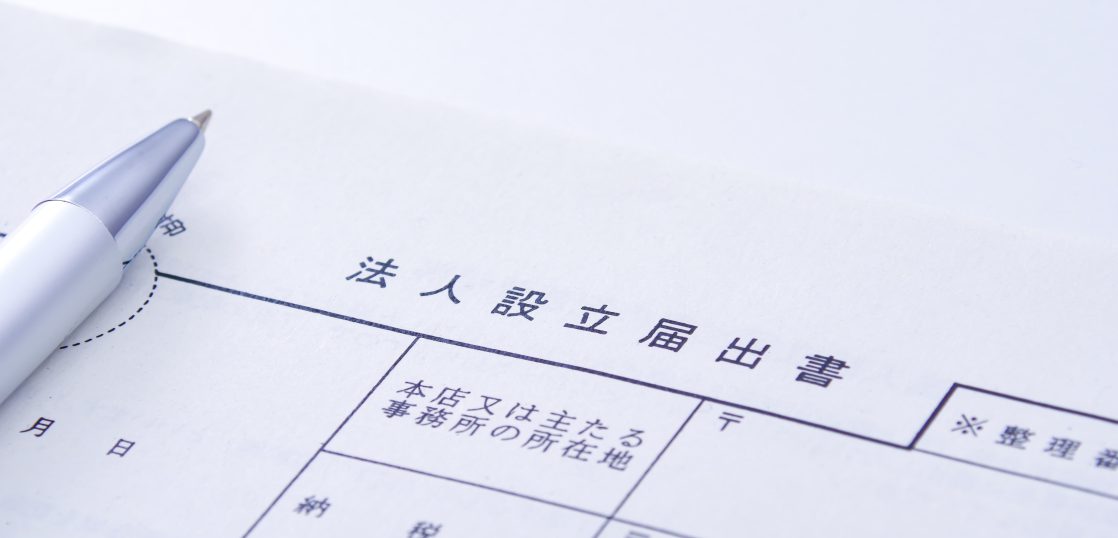これから会社を設立しようと考えている方で、税理士と契約するかどうかお悩みの方は多いと思います。また、顧問契約をするならば会社設立時・設立後どちらの方が良いのかも気になるのではないでしょうか。契約のタイミングによるメリットやデメリットをを紹介します。
会社設立時に税理士は必要?
会社設立の際に経営者が悩むことの1つが、顧問税理士との契約です。一人法人などの小規模企業の場合、経営者が経理も兼ねるため、業務が煩雑になりがちです。税務の知識がない場合には、どのような業務を行えばよいのかも頭痛の種なのではないでしょうか。そのため税務周りのことは専門家に任せたいと思っても、税理士と契約するのにもコストがかかります。起業したての場合、収入が軌道に乗るまでは不安も多いため、慎重に検討したいところです。
顧問税理士と契約するのであれば、会社設立の段階の方が良いのでしょうか。それとも必要性を感じてからにすべきでしょうか。
会社設立時に税理士を雇うメリットとデメリット
会社設立時からコストを覚悟してでも税理士を雇うメリットはあるのでしょうか。デメリットも含めて解説していきます。
会社設立時に税理士を雇うメリット
・設立手続きの代行をしてもらえる場合がある
昨今では会社設立を無料で代行する税理士も多く、煩雑な手続きを無料で代行してもらえることが会社設立時に税理士を雇う大きなメリットです。
ただし、この無料というのはあくまでも手続きの代行料のみになります。代行料以外に必要となる費用として、印紙代や定款認証料、登録免許税などがあり、これらは会社設立にかかる税金のようなものです。どのような手続きを踏んだとしても、これらの費用が約20万円はかかってしまいます。この税金である約20万円以外には費用負担はありませんというのが、「会社設立代行無料」というサービスになります。
さらに、この無料サービスは会社設立後の顧問契約とセットになっていることがほとんどであるため、依頼する際にきちんとした税理士を選ぶことが重要です。
・資金調達や税に関わることの相談ができる
会社設立に関してのノウハウを持っている税理士であれば、会社設立1年目にしかできない資金調達や節税などをアドバイスしてくれます。
補助金や助成金、融資は自治体によってさまざまな種類があるため、どれがベストな調達方法なのかわかりづらい可能性があります。税理士からは資金調達に関する最新情報を得られるだけでなく、事業計画書策定のアドバイスも受けることが可能です。
融資に関して不安がある場合は、融資面談への同席を依頼することもできます。また、設立時にどのぐらい資金調達すべきかということに関しても、的確なアドバイスがもらえます。助成金や補助金などは日々変更されるため、内容を把握するのも大変です。しかし、顧問税理士がいると利用できるものや最新情報を教えてくれる場合も多くなります。起業したての経営者には、特に心強いのではないでしょうか。
・決算期等のアドバイスももらえる
会社の設立手続きを行う際には、決算期を決める必要があります。設立手続きをするときに税理士を雇えば、決算期についても相談できます。設立時に税理士を雇うことで、今後の売上予想を分析し、適切な決算期についてアドバイスをしてもらうことが可能になります。
例えば事業内容や業界の特性上、秋頃(9月・10月)に最も売上が伸びるような場合、決算期を10月や11月に設定してしまうと、通年での利益予想が立てにくく納税額の予測が困難になります。思ったより売上が上がった場合、嬉しい反面、利益が上がりすぎて経費との調整がつかず、節税ができないかもしれません。
上記のような場合は、売上が最も伸びやすい時期より前の7月や8月にすることで、6月頃に1年の利益予想ができるようになります。ある程度正確に利益予想ができることで、経費を調整し節税の検討も可能です。日本では3月決算の会社が多いため、なんとなく3月を決算月に選んでしまう人も多いですが、業界によっては3月を避けた方がいいケースや、他に最適な決算月がある場合もあります。
決算期は設立手続きの時点で決める必要があり、設立手続き後に決算期を変更することは容易ではありません。このことを踏まえると、税理士からプロならではのアドバイスをもらえることはメリットだといえます。
会社設立時に税理士を雇うデメリット
・高い費用がかかる可能性がある
顧問契約が会社設立代行とセットの場合、会社設立後に必ず顧問契約を行う必要があります。先に顧問料の詳細について確認をしていないと、想定より高額な顧問料が必要になる可能性があります。設立代行を契約する前に、以下のことは必ず確認しておきましょう。
- 年間どのくらいの費用がかかるのか
- 顧問契約の内容にはどのようなサービスが含まれるのか
- 1年後、2年後にどのくらい費用が必要になるか
- 顧問契約料以外に必要になる費用があるか
設立代行が無料であったり費用が安かったりする反面、顧問料が割高なケースや、1年目のみ顧問契約料が安いケースなどもあるので注意が必要です。
・合わない税理士を選んだ場合でも契約する必要がある
上記と同じ理由になりますが、会社設立代行が顧問契約とセットになっている場合、相性が悪い税理士だったとしても必ず顧問契約をする必要があります。
顧問契約がセットで会社設立代行を依頼する場合は、依頼する前に「信頼できる税理士か」「自分と相性が合いそうか」などを見極めることが重要になります。どうしても合わない場合など、後々税理士を変更することは可能ですが、契約の内容にもよるためしっかり確認しておきましょう。
会社設立後に税理士を雇うメリットとデメリット
会社設立時に税理士を雇うメリットをご紹介しましたが、会社設立までは単発で司法書士にお願いするなど、特に税理士を必要としないこともあるでしょう。しかし、会社設立後に税理士の力を借りたいと思うこともあるかもしれません。設立後に税理士を雇うメリット・デメリットについてもご紹介します。
会社設立後に税理士を雇うメリット
・純粋に「顧問税理士」を他社と比較しながら探せる
会社設立後に初めて税理士と契約する場合、純粋に顧問税理士としての税務のサービス内容や顧問料などで税理士を選べます。また、実際に事業を運営しながら、本当に顧問契約が必要かの判断もでき、どのようなサービス・サポートを受けたいかを見極めることも可能です。
会社設立後に税理士を雇うデメリット
・会社設立時にかかる費用が高くなる可能性がある
無料の会社設立代行を頼んだ場合に比べて「会社設立にかかる費用」が高くなる場合があります。また、設立に関する煩雑な手続きに手間をとられるかもしれません。
後々顧問税理士を雇う予定があるのであれば、会社設立時に設立代行が無料の相性の良い税理士を選ぶことも検討してみましょう。顧問契約の内容にもよりますが、トータルでのコストを抑えられる可能性があります。
・設立時に決めてしまったことが容易には変更できない
資本金の金額、決算期や役員報酬など会社設立時に決めてしまったことは、後で変更することが難しくなります。変更できない訳ではありませんが、ほとんどの場合は費用がかかります。また最適な決算月や役員報酬を設定できていない場合、うまく節税できない可能性があるため、設立時に税理士に相談できると無駄がありません。
・税理士と契約したタイミングが合わない場合がある
決算月が差し迫った状態で全く記帳していない場合や、決算の申告期限をすぎてしまっている場合、税理士と契約できない可能性があります。
特に12月〜翌年5月頃は税理士も繁忙期である可能性が高く、1から帳簿付けが必要な場合などは対応が難しいことも考えられます。結果、せっかく相性が良さそうな税理士を見つけても、顧問契約はできない可能性があります。
まとめ
初めての会社設立の場合、少しでも不安があれば税理士に相談しながら進めることをオススメします。会社設立時の手続きも専門家の力を借りるとスムーズで、わからないことも相談できるため安心です。できるだけ不安をなくし事業に専念できるならば、コストも必要経費として高くはないかもしれません。一方、なるべくコストを掛けたくないという場合は、今回紹介したデメリットを考慮しつつ、会社設立後に必要に応じて顧問契約を検討しましょう。
記帳は自社で可能なため、とりあえず顧問税理士はつけずにやってみようと考えている経営者の方には、法人決算オンラインがオススメです。法人の確定申告に関しては専門知識が必要なため、プロに任せた方が良いといえます。法人決算オンラインは、クラウド会計認定アドバイザー税理士が自ら作り上げた決算申告ソフトウェアです。年間売上高が5億円未満であれば均一料金79,800円(税抜)にてご利用可能です。300項目以上の申告チェックプログラムで、最適な申告を行います。自社で会計を頑張りたい場合は、必要に応じて税理士の力を借りながら、決算法人決算オンラインを利用して自社に最適な会計体制を整えましょう。